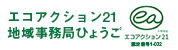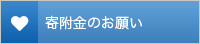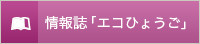令和6年度論文
水環境科(水質環境担当)
食物連鎖モデルを用いた瀬戸内海播磨灘の水質・生態系への栄養塩類負荷量の影響評価
古賀佑太郎, 嶋寺光, 佐藤祐一, ピントス・アンドリオリ・ バレンティナ, 鈴木元治, 松尾智仁, 近藤明
水環境学会誌 ,47(5), 151-161 (2024)
現在, 瀬戸内海播磨灘では, 栄養塩類である全窒素 (TN) の陸域からの流入負荷量を増加させることで, 生物の多様性と生産性を確保する取り組みが実施されている。本研究は, TN陸域流入負荷量の増減によって, 海のTN濃度と生態系 (植物プランクトン, 動物プランクトン及び魚類) に与える影響を, 食物連鎖モデルを用いて予測した。モデルの生態系パラメータは, モンテカルロ法により複数の組み合わせを算出した。計算対象海域を水質環境の異なる北部沿岸域と中央南部海域に分け, それぞれで, TN濃度と植物プランクトンのバイオマス量に良好な再現性が得られた。予測計算の結果, 2010年代の陸域からのTN負荷量を10倍まで増加させた場合に, TN濃度は北部沿岸域で現在の約1.9倍, 中央南部海域では約1.3倍にまで増加した。また, 魚食性魚のバイオマス量も増加し, 両海域で約1.2倍まで増加した。
東京湾におけるCO2およびO2海面フラックスの長期リアルタイム・モニタリング:気候変動に対応できる沿岸環境・生態系モデルの基礎として
藤原建紀, 加地智彦, 鈴木元治
水環境学会誌 ,47(4), 113-128 (2024)
東京湾において,水質,流速,気象の連続測定データを用い,流入した栄養塩が一次生産となり,大気からCO2を吸収し,O2を放出する過程を調べた。O2およびCO2 のフラックスは,気象変化に伴って,吸収と放出が,互いに逆位相で頻繁に切り替わった。生物の代謝によるO2:CO2比は約1:1 であるのに対し,海面フラックスのO2:CO2 比は約10:1 であり,それぞれ年平均で放出65.4 および吸収7.4 mmol m-2 d-1であった。O2の平衡化時間は短く,栄養塩流入による一次生産で生じたO2は速やかに大気に放出された。一方,CO2の平衡化時間は,湾内水の滞留時間よりも遙かに長く,湾内のCO2吸収量は,栄養塩流入で生じるCO2吸収能力の約1/10 とみられた。滞留時間の短い内湾ではO2フラックス測定が重要である。また,湾内の鉛直循環流を実測し,湾全体の一次生産と,O2およびCO2輸送の概念図を示した。
貧栄養化にともなう有機物の難分解化,COD上昇
藤原建紀, 鈴木元治
水環境学会誌 ,47(A)(10), 365-369 (2024)
2000年以降,東京湾や伊勢湾,大阪湾のTN・TP濃度は顕著に低下し,赤潮は減少し,透明度も上昇し,富栄養化対策は成功したとみられる。しかしながら,有機汚濁指標のCODはほとんど低下せず,海域によってはCODが増加する傾向さえみられる。このパラドックスの原因究明を行った。まず,海域とその集水域における有機物の生成・分解について概観し,特に情報の少ない溶存有機物の生成場所は,河口域で作られていることを示した。次に,貧栄養化によって有機物の変質,難分解化が起こり,CODが上昇していることを示した。
大気環境科
Developing an Automatic Asbestos Detection Method Based on a Convolutional Neural Network and Support Vector Machine
Matsuo, T, Takimoto, T, Tanaka, S, Futamura, A, Shimadera, H, Kondo, A
Applied Sciences, 14(20), 9408(2024)
アスベストを含む建物の解体に伴って発生する微細なアスベスト繊維は人体に深刻な健康被害をもたらすおそれがある。そのため、解体現場ではアスベスト繊維の環境中への飛散を防ぐため漏出のモニタリングが行われている。アスベスト繊維のモニタリングは顕微鏡観察で行われているが、多大な人手を要する。そこで本研究では、位相差顕微鏡画像からアスベスト繊維を自動検出する機械学習モデルを開発した。モデルは、訓練済畳み込みニューラルネットワークを基礎とし、全結合層またはサポートベクターマシン(SVM)を分類器として用いた。また、畳み込み層のファインチューニング、教師データのクラス重み付け、ハイパーパラメータ調整がモデル性能に及ぼす効果が評価された。その結果、モデルの全体的な精度を向上のため、分類器にはSVMが選択された。また、ファインチューニングはモデルの性能を向上させた。最適化された検出モデルは、F1スコア0.83という高い分類性能を示した。本研究の結果は、アスベスト繊維を効果的に検出するための貴重な知見を提供するものである。
船舶排ガス中に含まれるPM の主要成分について-一般海域における船舶燃料油硫黄分規制による燃料転換前後の実船における排ガスの変化-
楠将史, 吉田明輝, 速水健斗,今吾一,中坪良平, 二村綾美, 大下佳恵, 髙石豊, 岡村秀雄
日本マリンエンジニアリング学会誌, 60(2), 75-81(2025)
我が国の大気中微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準達成率は近年改善がみられる。しかし,未だこの環境基準を達成できていない測定局が中国・四国地方の瀬戸内海に面する地域に集中している。その理由の一つとして,瀬戸内海を航行する船舶の排ガスの影響が指摘されている。本研究では,MARPOL 73/78 に基づく2020 年SOX 規制により,スクラバ等の後処理装置を搭載しない船舶では,低硫黄燃料油への転換が必要となったため,燃料油転換前後の船舶から排出される粒子状物質(PM)を実船実験により捕集し,PM 主要成分の特徴について調査した。環境省においてPM2.5は大気中に浮遊する小さな粒子のうち,粒子の大きさが2.5 μm以下の非常に小さな粒子,日本産業規格(JIS)においてPMは排気に含まれる粒子状の物質とされている。また,PM 捕集時のディーゼル機関運転データを計測し,PM との関係性も併せて調査するとともに,瀬戸内海沿岸部(兵庫県環境研究センター屋上)で測定したPM2.5の組成を加え考察した。